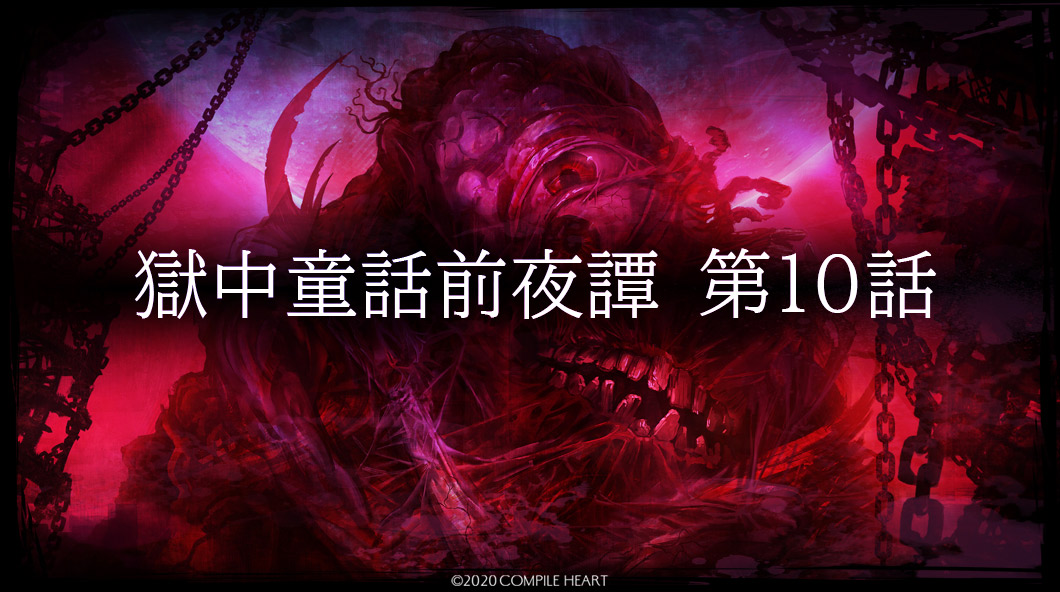 幼い頃の記憶は、あまりない。
幼い頃の記憶は、あまりない。みんなに「お母さん」と呼ばれていた人が、よくあたしの世話をしてくれていたように思う。他にも何人か、黎明の初期幹部だった人たちがいたらしい。でも正直、誰のこともよく覚えてない。
監獄塔が倒れた後、黎明初期幹部の記憶を持つという人たちに会った。彼らはあたしに「大きくなった」と言ってくれたけど、正直ぴんと来なかった。
そんな彼らの記憶も、少しずつ薄れているらしい。視子は「それでいい。彼らは彼らなんだから」と、少し寂しそうに言っていた。
だから、あたしがはっきり家族だと思えるのは、黎明が再編成されてからのメンバーだけ。つまり、ハルとか視子とか、血式少女隊のみんな……それと、お父さん。
監獄塔で起きたことは、まだ受け入れきれてない。あんな目に遭ったのに、あんなことを言われたのに、あたしはまだ、考えてる。
本当に全部が、嘘だったのか。
楽しかった。優しかった。愛されてると思ってた。
分かってる。あたしのそんな馬鹿なところが、大きな嘘に気付けなかった原因だ。そのせいでたくさん間違えた。悲しいことが増えた。あたしたちの戦いが一番いい終わり方を迎えたなんて、とても思えない。
それでも。
「おねーちゃん、どうしたの?」
最悪じゃない。
みんなで一緒に、今日という日を迎えることができた。本当ならここにいなかったはずの、人魚姫まで一緒に。
「ううん、なんでもないよ」
心配そうにあたしの顔をのぞき込んでくる人魚姫に、明るく笑ってみせる。
あたしたちは、大きな希望へ向かって歩き出そうとしている。
だから、くよくよ悩んでる場合じゃない。
あたしは、最初の血式少女として……みんなのお姉さんとして、今度こそみんなを守ってあげないといけないんだ。
お父さんに聞いたことがある。黎明っていうのは、夜明けっていう意味なんだって。
もうすぐ、夜が明ける。
そうしたら、あたしたちは。
 ◯
「意外と、明るくないのね、上」
◯
「意外と、明るくないのね、上」地上を見上げて、アリスはぽつりと呟いた。
「うん。まだ、本当の夜明けには早いのかもね」
同じように天を仰ぐジャック。太陽を見たことがない二人には夜明けがどれだけ明るいのか分からないが、話に聞いて想像していたよりは、地上はまだ薄暗かった。
「上に出てしまえば、もっと明るくなるのかしら」
「きっとね。それに、暖かいらしいよ」
「旅人がマントを脱ぐくらいに?」
「あはは。それもなんだか、ずっと前のことのような気がするね」
小さく笑い合う。
「……本当に、ここまで来れたんだね」
「そうね……」
「黎明のみんな。タイヨウのみんな。血式少女のみんな。マモルたちに、つうと人魚姫さん……みんなのおかげだよ。みんなが諦めなかったから、みんなで地上に行けるんだ」
ぶつかったこともある。すれ違ったこともある。けれど最後には、全員でこの地下監獄から抜け出せる。
心配が無いわけではない。地上にも、この地下と同じようなジェイルが存在するかもしれない。けれどそれはもう、僕たちにとっては決して絶望じゃない。ジャックは強く、そう信じていた。
「でもね、ジャック。確かにみんなのおかげなんだけど、わたしにとってはやっぱり、あなたのおかげなのよ」
「僕の?」
きょとんとするジャックの瞳を、アリスは真っ直ぐに見つめて言う。
「あなたがいなかったら、きっとわたしはとっくに諦めていたわ。脱獄も、拷問に耐えることも、生きることも……友達を、作ることも」
アリスは、自分の髪に飾られた十字の形のアクセサリーに手を触れる。
「あなたよジャック。あなたなの。わたしは太陽を知らない。だけど分かるわ。太陽というのはきっと、あなたのように暖かく、私を照らしてくれるの」
「アリス……」
「ねぇジャック、覚えてる? 監獄の中で、わたしに言ってくれた言葉」
ジャックは思い出す。監獄の中で、いったいいくつの言葉を交わしたことだろう。けれどなぜか、今アリスが求めている言葉がなんなのか、すぐに分かった。
「僕は君を守るから。だからきっと、一緒に脱出しよう」
アリスは、嬉しそうに微笑んで。
「ええ。わたしも……ジャックを守るから。きっと一緒に……」
二人は手を繋ぎ、まだ薄暗い地上を再び見上げた。
あの先に、太陽がある。
 ◯
――そして、名前のない登場人物がまた一人。
◯
――そして、名前のない登場人物がまた一人。地下監獄の解放地区と呼ばれる場所で目を覚ましたとき、彼は自分のことをほとんど覚えていなかった。名前も、過去も、自分がなぜここにいるのかも。
彼にはまだ、名前がない。
もしも誰かが、彼に名前をつけたなら。
そのとき彼は、物語を動かす力を手に入れるだろう。
 ◯
これより始まるは、運命からの脱獄劇。
◯
これより始まるは、運命からの脱獄劇。絡み合ういくつもの糸が織りなす、終演の物語。
絶望の闇に閉ざされた世界に、希望の光を取り戻すため。
血にまみれた少女たちは、忘却と再生の循環謳歌を奏で始める。