第6回 ギインドールズは新たな戦いへ
 「サン、ニ、イチ、キュー!!」
「サン、ニ、イチ、キュー!!」「え、えーと、こ、国民のみなさん、コバンワ。な、内閣ソーリ大臣です、いや、ソーリの神貫ナツメです」
「カーット!!」
カメラの後ろにいる男性が、大慌てで撮影中断を指示した。
「……え、あ、あ、スミマセン」
「困るよー総理。もっと自然な感じでお願いします」
「普段どおりにやろうとは思ってるんですけど……」
「全然できていないわ……」と、ナツメの右隣に座る西園寺チヨがつぶやいた。「いま、壊れたロボットみたいだったわよ」
チヨの言葉に、ナツメの左隣に座る漆原ホタルも、コクコクと小さく首を縦に振っている。
しかし、そのホタルの表情もまた、普段とはまるで違いこわばっていた。
「みなさん、魔物との戦いに比べれば恐れることはありまセンヨ。もっと肩の力を抜きまショウ」
ホタルの隣に座る霧隠ミクリだけは、唯一普段と変わらない柔和な笑顔を浮かべ、ナツメたちに向けて穏やかにそう言った。
「テイクツー、いきますよー。総理も官房長官も顔がちょっと怖いな、笑って笑って……サン、ニ、イチ、キュー」
「み、みなさん、こんばんは。わたしが、な、内閣ソーリの……大臣の、神貫ナツメと申し……」
「カット、カット、カーット!!」
……科技葉原Q-BOXの一室でなぜこのような撮影が行われているのかというと、内閣の支持率を上げるためのPR作戦の一環だった。
ナツメたち電脳戦術内閣は、二ホンを襲う魔物たちに対抗すべく発足された。
しかしナツメたち内閣は、選挙によって国民の信任を受けた代議士でもなければ、有識者として指名された大臣でもない。魔物の襲来によって崩壊した前内閣が、緊急時の内閣発足に関する時限立法を事前に成立させて、その法案に則るかたちで組閣、発足されたのが電脳戦術内閣だった。
そのため、正式に国民の信任を受けてできた内閣ではないからこそ、国民の支持を保ち続ける必要があった。でなければ、電脳戦術内閣はただの私設軍隊と変わらなくなってしまう。
魔物たちとの戦う姿を常に国民に向けて中継しているのも、そうした理由からだった。
しかし、見た目にはただの女の子でしかないナツメたちを、この国の内閣として認め難いと考える人たちも少なからず存在する。
そこでナツメたちはさらに支持率を上げるため、何かいい方法はないかと、日々頭を絞って考えていた。ああでもないこうでもないと、散々悩んだ挙げ句、ダメ元というか誰かがほとんど冗談で提出したのがこの《PR動画を撮影したい!!》法案だった。そして、なぜかあっさりとこの案が可決されてしまったのである。
西園寺チヨの場合。
「私は、内閣官房長官を務めさせていただいています。尊敬する人物は、もちろん叔父様です。叔父様のような官房長官になれるよう心がけています。え? 特技ですか? 強いていえばフルートかしら。え? え、ええ、かまわないですけれど……(演奏後フルートから唇を離し)こんな感じですけれど、……あの、私がフルートを吹いているところが、内閣のPRになるんですか??」
漆原ホタルの場合。
「こ……こ、こんにち……は。漆原ホタル、です。……あ、一応、ホタルが、防衛大臣です……ホタル、運動はあんまり、得意じゃなくて。でも、……プロレスを見るのが好きです。……え? お父さんを知ってるんですか? うれしい……。ホタルも、いつかお父さんみたいになりたい……え? これ、お父さんと同じデザインのマスク……? かぶって、ポーズをとればいいんですか? なんかうれしい……でも、力こぶ、全然ないよぉ」
霧隠ミクリの場合。
「よろしくお願いいたしマス。電脳戦術内閣では外務大臣を務めていマス。この格好デスか? はい、ワタシは普段からこうした巫女の服を愛用していマス。二ホンの文化は素晴らしいデス。皆サンももっと二ホンの古き良き文化に触れてくださると嬉しいデス。あ、これは女性の忍者……くのいちの衣装デスネ!! 撮影でこんな素敵な衣装を着させていただきありがとうございマス! 手裏剣マデ!! ……投げてみてもイイデスか?」
このように、内閣全員での撮影のほか、撮影ディレクターの指示で、個別インタビューや個々の撮影なども行われていった。ナツメも自身の内閣での役割を説明し、ディレクターの要望で中学時代の体育祭等の写真を公開したり、趣味で集めているチンアナゴのグッズまで撮影されてしまった。
ひととおり個別の撮影を終えた後、ナツメはディレクターから「最後に国民に向けて総理から何かあるかな?」とカメラを向けられた。
ナツメは少し考えた後で「……じゃあ、少しだけ」と、自身の思いを語り始めた。
「ふぅ……ええと、国民のみなさんは二ホンがこんなことになって、いまとても大変だと思います。内閣のわたしたちが、こんな……普通の女の子たちばかりなのも、不安ですよね……わたしたちも……わたしだって、怖いです……だって、わたしは、ついこの前まで、ただの女子高生だったんですから。友達とおしゃべりをして部活をやって、授業ではたまに居眠りなんかしちゃったりしたけど、そんな普通の女子高生でした。そのわたしがどうして、魔物と戦わなきゃいけないんだろう? すごく不思議だし、どうしてわたしなんだろうと、いまでも思うときがあります」
ナツメは言葉を切り、1度俯き、そしてもう1度しっかりとカメラを見据え「でも」と続けた。
この放送を見る国民に向けて、何より、カメラの向こうの親しい人たちの顔を思い浮かべて。
「……わたしには、大事な人たちがいます。おかーさんやおとーさん、友達のみんな、近所のおじさんやおばさん……。わたしはもう1度、みんなと楽しく暮らせるようになりたい。おしゃべりしたり、遊びに行ったり、ときどき喧嘩したり、怒られたり……。この放送を見ているみなさんと、わたしはもう1度、そんな普通の生活を送れるようになりたいです。……だから、わたしにできることがあるのなら、全力でがんばります。もしわたしを信じてもらえるなら、少しでも応援してくれるとうれしいです。みなさんの支持が、わたしたち電脳戦術内閣の力になるので、どうかよろしくお願いします」
ナツメはカメラを真っ直ぐに見つめ、そして深く、深く一礼した。
その場にいた撮影クルーたちの間で、自然と拍手が湧き起った。
ついにすべての収録が終了しようとしていた。
「「以上わたしたち、ギインドールズでしたっ!」」
だが……4人で最後の挨拶を言い終わるというタイミングで、突然Q-BOX全体に、けたたましいサイレンが響き渡る。
「ハイ、ええわかりました……大変だよ、みんな」
スマホでどこかと連絡を取っていたハスミが、厳しい表情をナツメたちへと向けた。
「……出たんだね?」
「すでに自警隊が交戦中、行ける?」
「もちろん!!」
言うが早いか、ナツメたちは撮影クルーに一礼をすると、表情を戦う者のそれに切り替えて、すぐに部屋から飛び出して行った。
カメラは彼女たちのその表情と背中を、最後までしっかりと捉えていた。
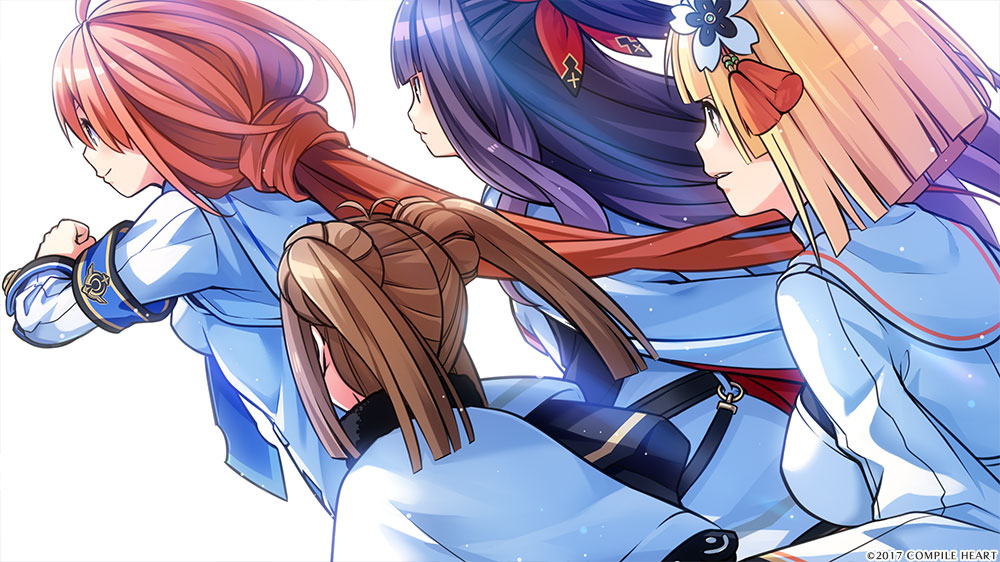
彼女は、避難所に備え付けられたモニターを見ながら、涙がこぼれるのを抑えられなかった。
昨晩、いつものようにいまは離れて暮らす娘からの電話で、この放送のことを知らされた。
「良かったらおかーさんも見てね♪」
いつものように明るい調子で娘は言った。幼い頃から天真爛漫で太陽のような娘だった。
そんな娘が、どうしてこんな過酷なさだめを背負わなければならないのか。中継される娘の戦いを見ながら、いつもそう思っていた。電話口の娘は明るいけれど、本当は毎日怖くて泣いているんじゃないだろうか。そうした不安ばかりだった。
でも、いま流れている放送の中で、娘は彼女が知っているのと同じ明るいままの娘だった。
放送の最後、仲間たちと魔物との戦いに赴く娘の姿を、その背中を見て、彼女は本当にナツメを想った。そしてまた、放送の中で娘が言ったように、必ず一緒に暮らせる日が来ることを、強く願い、隣で自分と同じように目を潤ませている夫に、そっと寄り添った。
